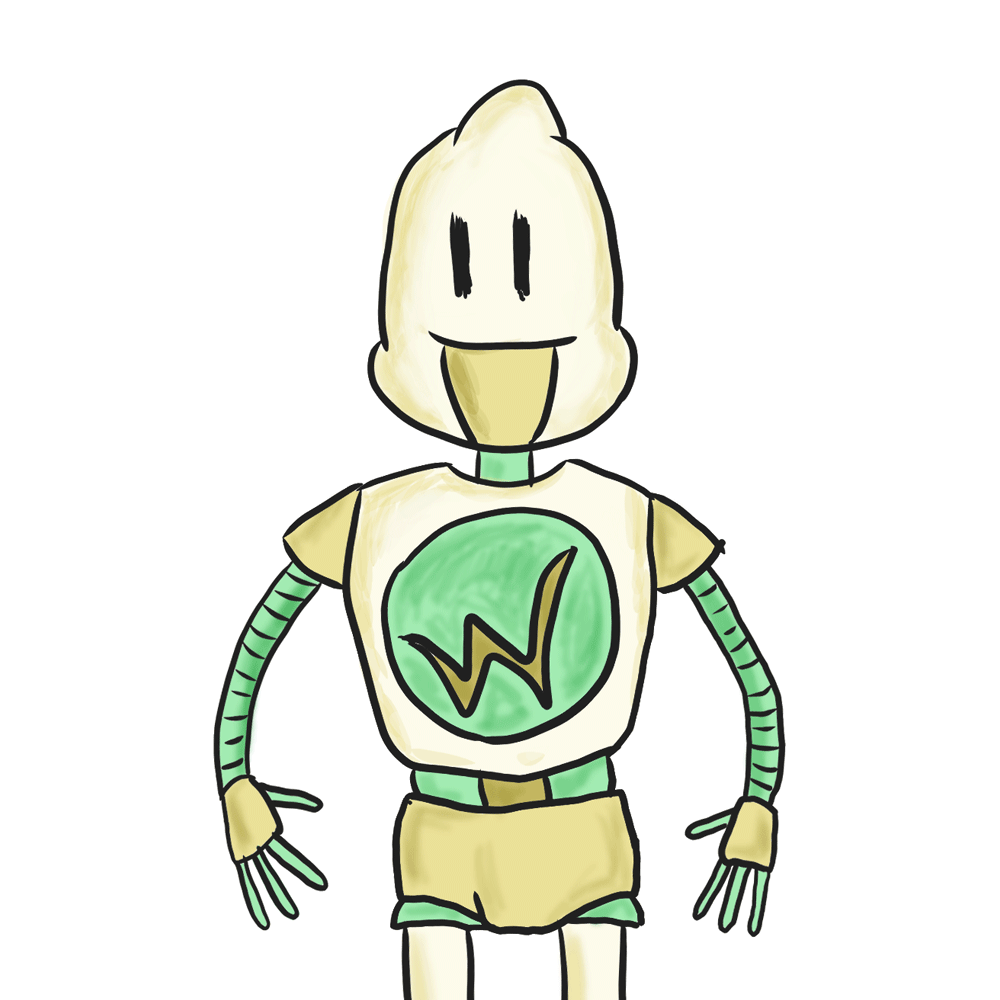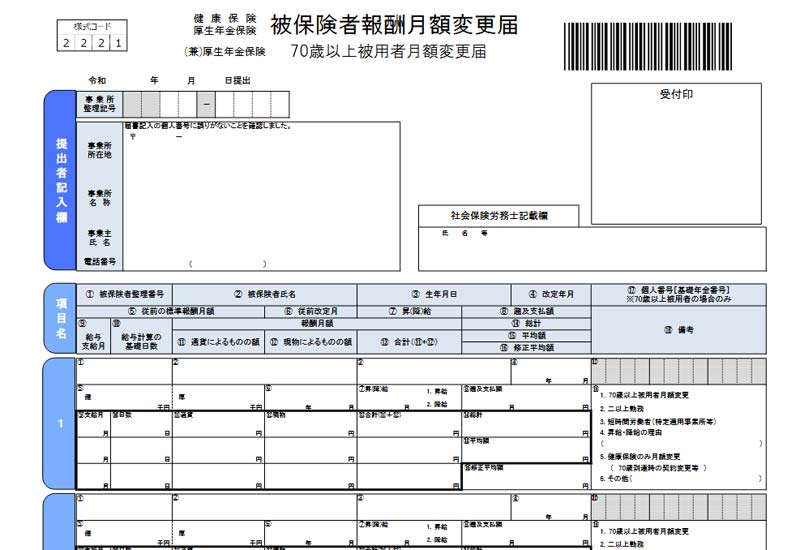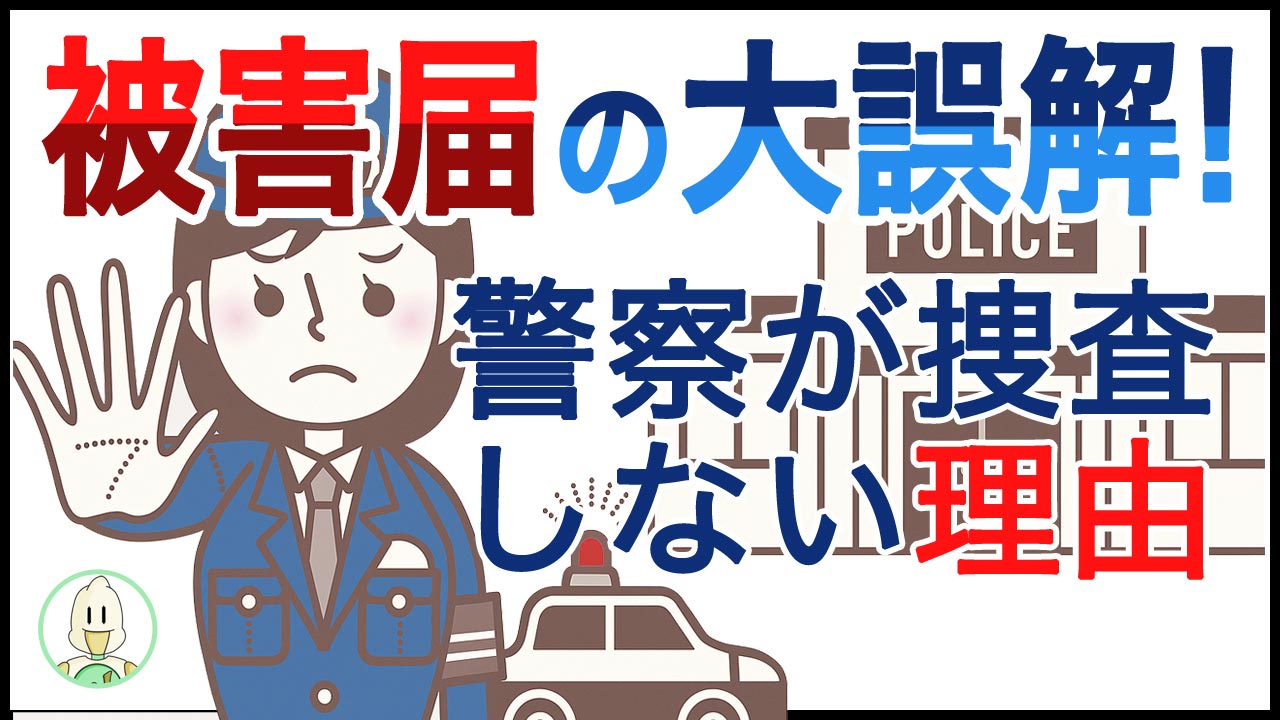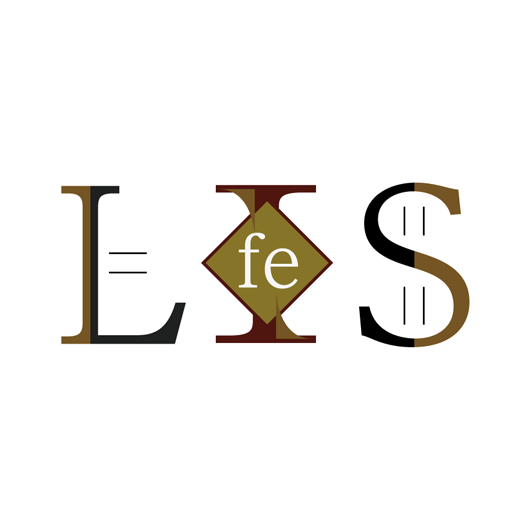2025.05.18 Sun 
雇用が企業を破壊する-パナソニック再び1万人のリストラへ

待ったなしの人員整理が大企業を襲う
大手企業のパナソニックが、再び大規模な人員削減に踏み切ります。グループ全体の約5%にあたる1万人を対象に、主に営業や管理部門を中心としたリストラを進めると発表しました。これは、国内で5000人、海外で5000人の削減を想定しており、今年度中に実施される見込みです。
理由は、収益が伸びない事業からの撤退や、国内外の拠点の整理・統合など。要するに「利益を生まないところにはもう人を置けない」という判断です。
実はパナソニックが大規模な人員削減を行うのはこれが初めてではありません。2001年には、初の赤字を受けて1万3000人を早期退職に、2011年には三洋電機の子会社化の影響でおよそ4万人もの削減が行われました。
こうしたニュースは、単なる「大企業の経営判断」として片付けられがちですが、私たちにとっても決して他人事ではありません。長く勤めていても、会社の都合で突然職を失うかもしれない――そんな不安を、現代の働く人たちは常に抱えているのです。
すでに10%の労働者が消えた?リストラの冷たい現実
パナソニックは2022年4月、グループ全体の体制を「持ち株会社制」に切り替えました。これは、各事業会社に経営の自由度を与え、よりスピーディに成長を目指すための動きでした。
しかし、期待されていた「累積営業利益1.5兆円」などの経営目標は、2025年3月期までに達成できない見込みとなっています。こうした中、今年2月には楠見社長が「聖域なき構造改革」を宣言。人員削減も含めて、これまで以上に大なたを振るう姿勢を明確にしました。
実際、表に出ていないリストラはすでに始まっているのかもしれません。パナソニックの公式発表によれば、2024年3月末時点のグループ全体の社員数は22万8420人。一方で、ロイターが報じた2025年3月期末の見込みでは、連結従業員数は約20万7548人にまで減るとされています。
わずか1年で約2万人、つまりおよそ1割の社員が姿を消している計算です。子会社の売却や再編も影響しているかもしれませんが、これだけの雇用がたったの1年で減少している事実には驚かされるばかりです。
“知らない間に人がいなくなっていた”——これが、今の日本企業で静かに進行している現実なのです。
 資格試験の効力は限界がある
資格試験の効力は限界がある
15年で18万人の削減──まるでいくつもの街が消失
パナソニックがこれまでどれほど大規模な人員削減を行ってきたか、ご存じでしょうか。
2016年に『東洋経済』が発表した「正社員を減らした500社ランキング」で、パナソニックは堂々の1位。その時点ですでに、2010年3月期の約38万5000人から、2015年3月期には約25万4000人と、わずか5年で約13万人の従業員がいなくなっていました。つまり、毎年1万人以上のペースで人が減っていたのです。
その後も早期退職などの形でリストラは続き、ロイターによると2025年3月期末には従業員数が約20万7500人になる見込み。結果として、2010年からの15年間で、実に18万人もの従業員が削減された計算になります。
数字だけ見るとピンとこないかもしれませんが、18万人というのは、日本の小さい地方自治体の3〜4つ分ほどの人口に匹敵する規模です。つまり、「15年かけて労働者の街がいくつも消えた」のと同じくらいのインパクトがあるのです。
そしてこの流れは、パナソニックに限った話ではありません。特に電機業界では、こうした大規模リストラが“当たり前の経営戦略”として繰り返されているのが現実です。
企業が生き残るために、雇用が切り捨てられていく。そんな時代に、私たちは生きています。
 自治体レベルの雇用消失
自治体レベルの雇用消失
雇用が企業を追い詰めるとき
「雇用に手をつけるのは、つらく、申し訳ない思いです。ですが、今ここで経営の土台を変えなければ、10年後、20年後に持続的な成長は望めません」――。
これは、パナソニックの楠見雄規社長が2025年5月9日の決算説明会で語った言葉をわかりやすく変換した内容です。企業が黒字を維持している今だからこそ、将来のために人員削減という苦渋の決断を下した、という説明でした。
一見すると矛盾しています。利益が出ているのに、なぜ人を減らす必要があるのか? けれど、今の日本企業にとって「雇用」はコストであり、将来の競争力を保つための“調整対象”になっているのが現実です。
かつては社員を大切にし、共に歩んできた企業文化があったはずです。しかし今は、そうした考え方が通用しなくなってきている――それが、「雇用が企業を破壊する」とも言える時代の象徴かもしれません。
電機業界はその他の業界に比較しても、ここ15年近くで大規模リストラを次々と敢行している。
理由はいくつかあげられるが、国際競争の激化と技術革新の遅れや高騰する人件費、内需面では消費税増税でサプライチェーン全体の事業者負担増などの影響を受け業績不振が拡大し続けている点などが大きい。
これは電機業界だけでなく、雇用を維持すれば企業が存続できない世界市場での自由競争と国内の制度設計による変化が大きくなっていて、全産業や業態全般でいまだ出口が見えない状態であるといえる。
1989年、平成元年の世界時価総額ランキングの上位50位のうちの32社、つまり64%は日本企業であった。
20年後の2019年、平成31年にはトヨタ自動車がかろうじて43位に残っているだけだ。
しかもトヨタ自動車は輸出戻し税による国の税制優遇を受けてのランクインとなり、この優遇措置は現在は米国トランプ大統領の相互関税における非関税障壁として指摘されている点もあり、今後の自動車輸出企業は大きな影響を受けるのは間違いない。
かつては雇用コストを低減し利益率を上げるため、海外にたくさんの工場を建設して安い労働資源を活用してきた日本企業。
ところが、結果的に製造技術や人材流出を促進することになり、かつては雇用を輸出して収益率を上げていたはずが、いつのまにか雇用が大きな負担となり、大企業でさえも維持や存続が不安定視されてしまう最大の要因となっている。
雇用を安価に仕入れたことで、20年の間に逆に雇用に苦しめられる状況に陥ってしまった。
パナソニック楠見社長が言うように「20年後に持続的に成長できない」は、技術革新やグローバル化のスピードが急速に進む昨今では、それすらも懐疑的な状態であることは間違いない。
安価な雇用により収益を拡大させ、20年でその雇用により存続の危機にさらされるという皮肉な現実は、雇用拡大型の産業は今後はさらにリスク管理と正面から向き合う必要がありそうだ。
つまりマンパワーの母数で支えられている企業や業態は、ちょっとしたリバランスにより企業も労働者も一瞬にして危機的な状況に陥りやすいこと意味している。
 雇用が最大リスクとなる時代
雇用が最大リスクとなる時代
掲載情報につきましては当社が独自に調査、検証および収集した情報です。
情報の妥当性や確実性を一切保証するものでなく、情報や内容が訂正や修正、変更されている場合があります。 よって、当社サイトの利用により生じたいかなる損害等についても運営側にて一切の責任を負いません。掲載情報の修正・変更等をご希望の場合はお知らせください。