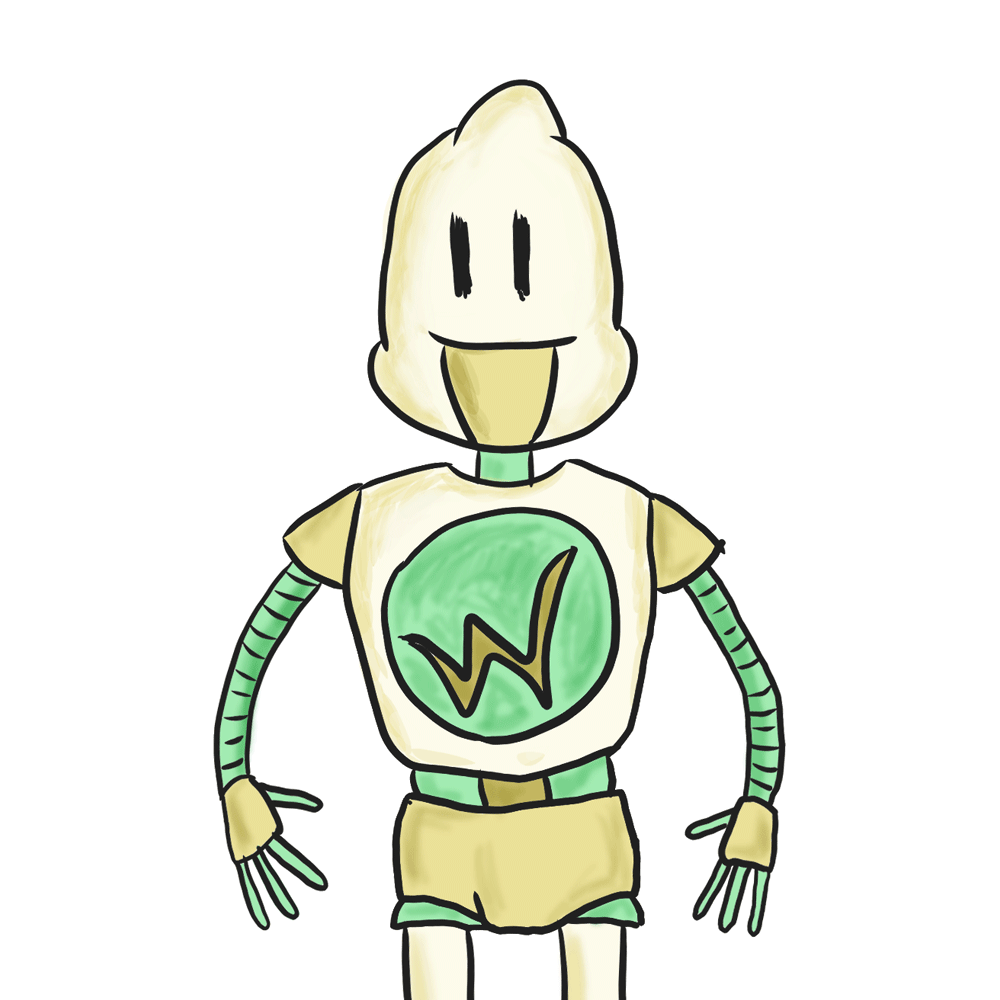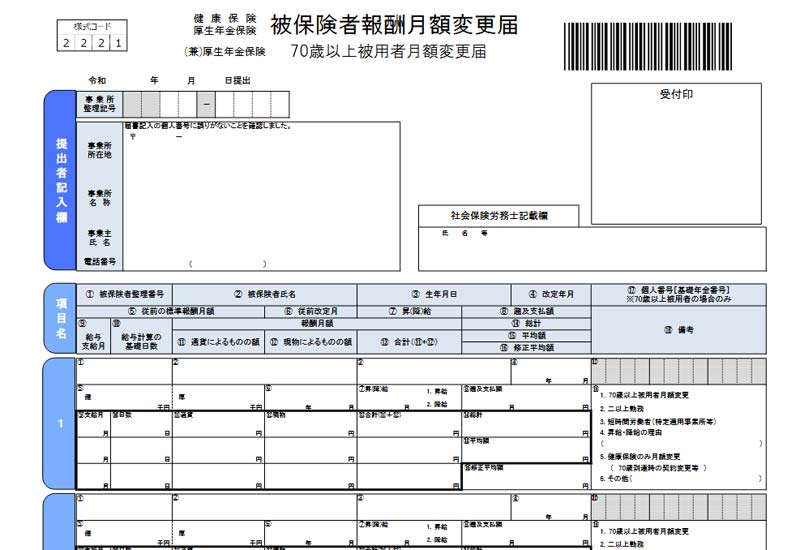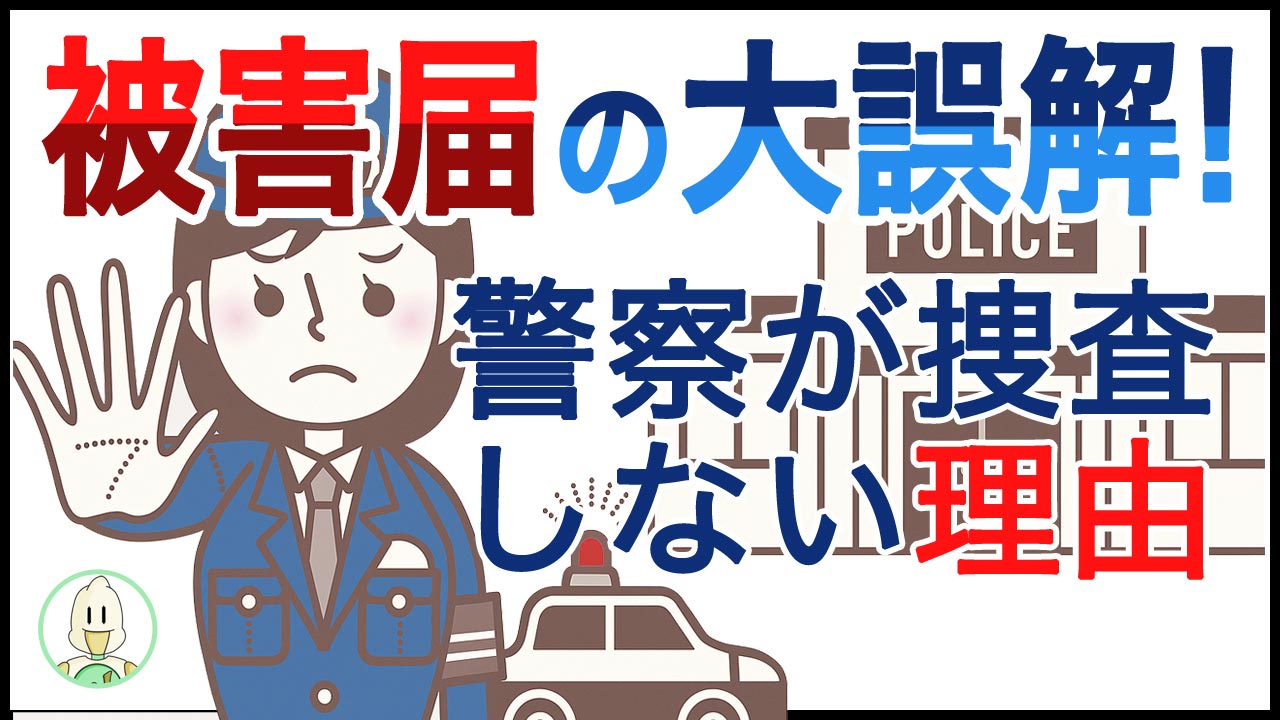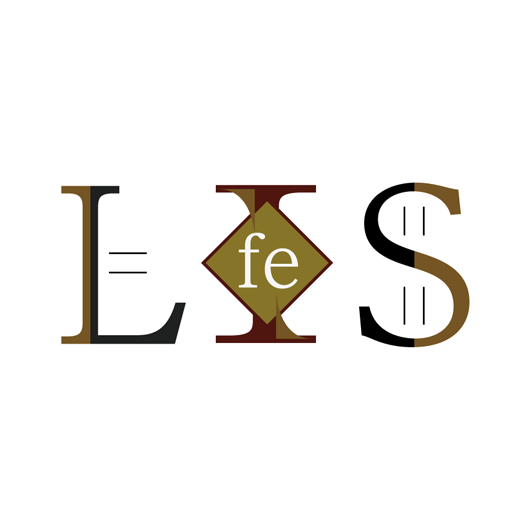2025.05.20 Tue
日産追加リストラ 2万人へ

日産2027年度までに2万人の人員削減へ
日産自動車は2024年度決算で6708億円の最終赤字を計上し、経営再建に向けて2027年度までに世界で2万人、全従業員の15%にあたる人員を削減すると発表しました。
業績悪化の要因には、アメリカ市場での販売費用増加や、過剰な生産設備の見直しによる5000億円超の減損損失がありました。
また、生産体制の効率化の一環として、世界に17ある完成車工場を10カ所に統廃合する計画で、国内拠点も対象となります。
さらに、アメリカの関税政策をめぐる不透明感から、2025年度の業績見通しは「未定」とされ、先行きへの懸念も強まっています。新社長エスピノーサ氏は「痛みを伴うが、今こそ抜本的な改革が必要」と強調しています。
神奈川の主力工場2つを閉鎖へ史上最大級のリストラ
経営難に陥っている日産自動車が、2027年度までに世界で7つの工場を閉鎖する計画を進めていることが明らかになりました。
国内では、神奈川県の追浜工場(横須賀市)と湘南工場(平塚市)の2つの主力工場を閉鎖する予定です。追浜工場は1961年から操業し、電気自動車リーフの生産で知られる日産の象徴的な工場でした。この2工場で約5100人が働いており、閉鎖により1933年の創業以来守ってきた神奈川県内の完成車工場がすべてなくなることになります。
日産がここまで追い込まれた背景には、世界的な販売不振があります。国内の生産能力は年約120万台なのに対し、実際の生産は約64万台にとどまり、特に追浜・湘南工場の稼働率は4割程度と、黒字化に必要な7〜8割を大きく下回っていました。その結果、2025年3月期決算では6700億円を超える巨額赤字を計上し、過去最大級のリストラに踏み切ることになったのです。
海外でも、メキシコ、南アフリカ、インド、アルゼンチンの5工場を閉鎖予定で、世界で2万人の人員削減も計画されています。かつてのゴーン改革を上回る規模の構造改革により、日産が業績回復を果たせるかが注目されます。
 史上最大級のリストラってなに?
史上最大級のリストラってなに?
日産の経営問題と日本経済の深刻な現実
日産自動車の経営体制は、異様な役員数の多さが目立ちます。過去20年間で役員数は増加し、特にゴーン体制以降、国際化の名の下に外国人役員を登用した結果、取締役会は多国籍企業らしい構成となりました。
しかし、意思決定の複雑化と責任の分散化が進み、深刻な赤字に陥っているにもかかわらず、膨大な役員数を維持し続けています。現場では2万人のリストラが計画される一方で、経営陣の数は減らず、この矛盾が日産の根本的な問題を物語っています。
さらに、2027年度までの2万人削減計画も、速度が遅く人数も不十分かもしれません。
日産には、重要な意思決定を先延ばしにする「夏休みの宿題を最終日にやる児童」のような企業DNAが染み付いており、危機的状況になってから慌てて対処する後手後手の経営が、今日の惨状を招いています。
先日のホンダとの合併交渉でも、日産の本質が露呈しました。
ホンダが提示した統合案に対し、日産側は自社の価値を過大評価し、対等合併を主張した結果、交渉は決裂し、日産は孤立無援の状態に陥りました。
これは、金遣いが荒く贅沢がやめられない「結婚適齢期を逃した大企業」の典型例です。長年にわたって高コスト体質を改善できず、身の丈に合わない経営を続けてきた結果、いざという時にパートナーを見つけることができなくなってしまったのです。
しかし、この問題は日産だけの話ではありません。今、日本のあらゆる産業や業態が大きく削り取られている状態にあります。
製造業から小売業、サービス業まで、多くの企業がリストラや事業縮小を余儀なくされています。特に深刻なのは政府の経済政策です。人件費だけを上げることを目標にしていますが、消費税増税、物価高、エネルギー価格高騰という重いコストが企業と家計を直撃しています。
これは極めて危険な兆候です。なかでも消費税は、日本全国の隅々まで行き渡り、あらゆる商業活動を侵食しながら、日本の成長を阻害する最大の抑止力として機能しています。この税制度こそが、日本企業の競争力を奪い、経済全体の活力を削いでいる元凶なのです。
日産の危機は、日本経済全体が抱える構造的問題の縮図に他なりません。根本的な改革なくして、真の再生はあり得ないでしょう。
 シュレッドジャパン
シュレッドジャパン
日産の現状と未来への課題
日産はかつて、自動車愛好者から高い評価を受ける名車を数多く生み出し、その栄光は今でも語り継がれています。
しかし、その輝かしい時代は30年以上も前の話です。現在は、全身から出血をしながら、かつての栄光に浸っている企業集団と化しています。
もちろん、優れた技術者やデザイナー、セールスマンや市場アナリストなど、実力のある社員はたくさんいるでしょう。しかし、そういった優秀な人材が活躍できない社風が色濃く、第三者の視点からも明らかです。
さらに、リストラには危険な側面もあります。人員を減らしたところで、優秀な人材が他社に移動してしまえば、競争力のある社員ばかりが残るわけではありません。
昔の栄光を懐かしむことも時には大切かもしれませんが、感傷にふけっている時間はほとんど残されていません。
日産の復活が見込めるのは、もはや自動車産業だけではありません。ロボット産業や介護福祉、ドローン開発など、新たな分野に目を向ける必要があるでしょう。
 栄光は捨てるためにある
栄光は捨てるためにある
掲載情報につきましては当社が独自に調査、検証および収集した情報です。
情報の妥当性や確実性を一切保証するものでなく、情報や内容が訂正や修正、変更されている場合があります。 よって、当社サイトの利用により生じたいかなる損害等についても運営側にて一切の責任を負いません。掲載情報の修正・変更等をご希望の場合はお知らせください。