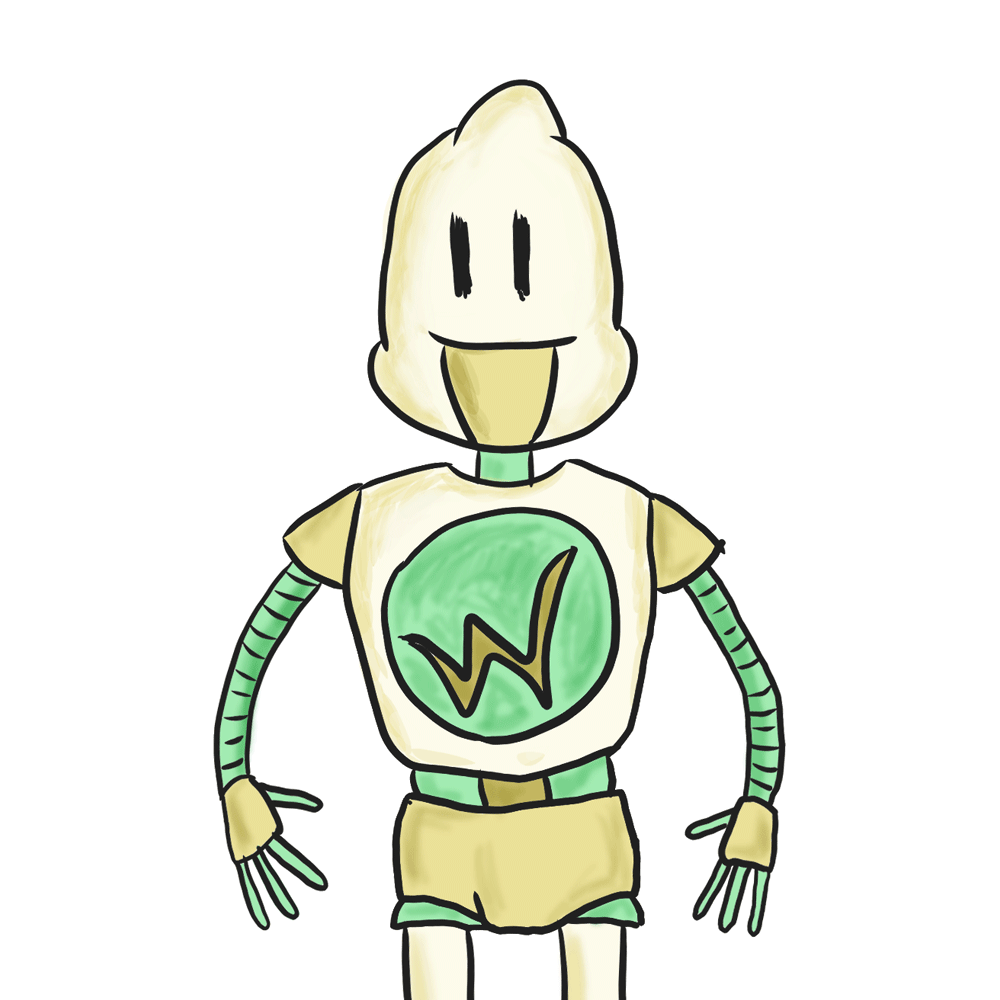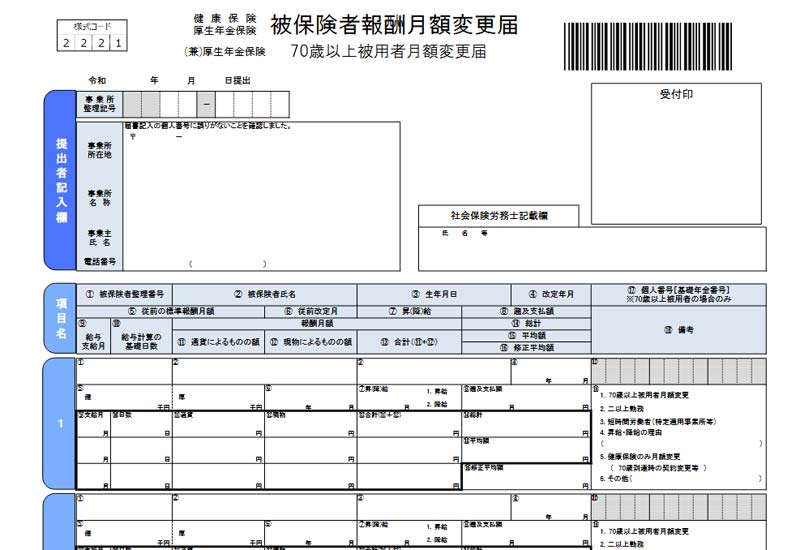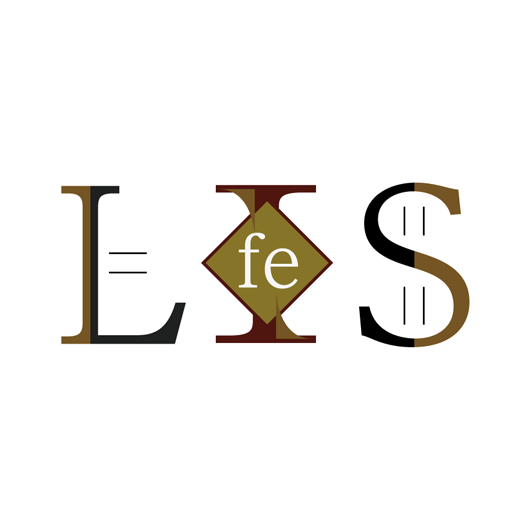2025.08.28 Thu
被害届の大誤解!警察が捜査しない理由
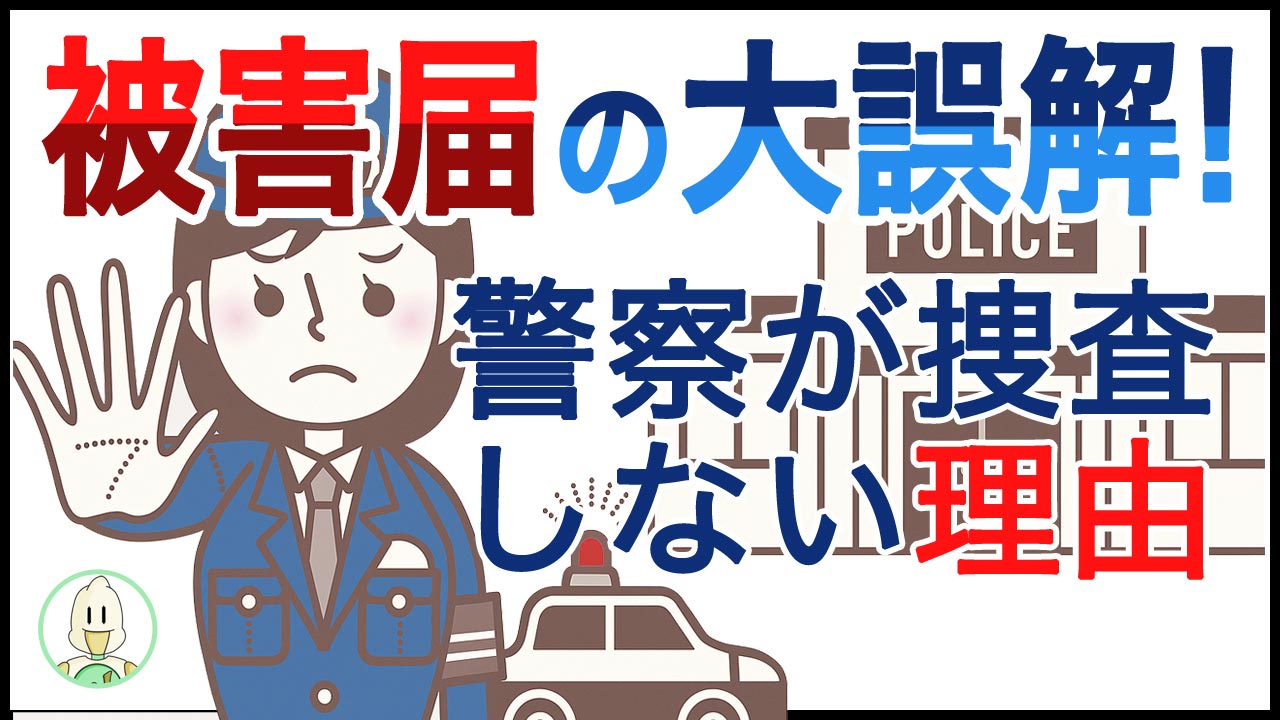
被害届=警察が動く、は完全な誤解
- 「被害届を出せば、警察が捜査してくれる」――
この認識は非常に多くの人が抱いていますが、法律上も運用上も、それはまったく正しくありません。
まず、被害届というのはあくまで「被害を届け出る」ためのものであり、警察に捜査の義務はありません。
つまり、受理されても、捜査されるかどうかは警察側の“裁量”に委ねられているのが実態です。
これに対し、「刑事告訴」や「告発」には明確な法的効果があります。
刑事訴訟法第230条では、「告訴があったときは、捜査機関は速やかに捜査を開始しなければならない」と定められており、
告訴状が受理された場合、原則として警察・検察は捜査義務が生じます。
被害届と告訴状は混同されがちですが、
- 被害届は「被害を知らせる」だけで、
- 告訴状は「処罰を求める法的行為」
この違いは極めて本質的です。
警察が“事件化しない”3つの理由
被害届を出しても、実際に警察が動かないのには、組織的・運用的な背景があります。
表面上は「捜査の必要がない」とされますが、実際には以下のような構造が関係しています。
第一に、証拠の有無が決定的です。
「被害を受けた」という主張だけでは、警察はほとんど動きません。
たとえ加害者が特定されていても、それを裏付ける証拠(録音・書面・履歴など)がなければ、被害届は“単なる主張”とされ、立件の土俵にも上がりません。
次に、民事と刑事の境界線です。
多くのトラブル――金銭の貸し借り、詐欺被害、ネット上の誹謗中傷、ストーカーまがいの嫌がらせなど――は、警察にとって“民事寄り”とみなされがちです。
刑事事件として処理するには、法的な構成要件(たとえば「詐欺罪」「脅迫罪」「名誉毀損」「著作権侵害」など)を満たしていなければならず、ここにハードルがあります。
さらに、リソースと優先順位の問題も深刻です。
現場の警察は、強盗・傷害・性犯罪・薬物事件などの“明確な刑事事件”を優先せざるを得ず、
被害額が少額だったり、加害者が不明だったりするケースは「事案性が薄い」として後回しになります。
警察官の裁量が極めて大きく、かつ、内部では“ノルマ”や“実績評価”が重視されるという構造が、こうした対応を助長しているというのが、複数の元警察官や弁護士の一致した見解です。
 運用上は被害届は受理される前提
運用上は被害届は受理される前提
被害届では動かない。告訴状との決定的な違い
ここで改めて、被害届と刑事告訴の違いに踏み込んでおきます。
被害届は、「犯罪の被害を受けたことを行政機関に知らせる」行為です。
一方、刑事告訴は、「加害者を処罰してほしい」と求める法的な意思表示であり、これが受理されると、警察は捜査義務を負うという決定的な違いがあります。
また、告訴は被害者にのみ認められる権利であり、一定の要件を満たせば検察は不起訴処分にした場合でも、告訴人には「理由の説明」を求めることができます。
そのため、刑事告訴は、被害届よりもずっと強力な手段です。
しかし、告訴状は形式や記載内容に厳格なルールがあり、弁護士の助力なしに通ることはほぼありません。
逆に言えば、弁護士が適切に告訴状を作成し、証拠を整理して提出すれば、警察も「放置できない案件」として扱わざるを得ないのです。
 被害届は行政期間へのお知らせ行為
被害届は行政期間へのお知らせ行為
本気で動いてもらうために今すべきこと
被害届を受理させ、なおかつ実際に警察を動かしたいのであれば、戦略的に動く必要があります。
そのためにはまず、「どんな被害が受理されやすいのか」、「警察が関心を持つ要件とは何か」を知る必要があります。
現実として、被害届が比較的受理されやすいのは以下のようなケースです:
- 加害者が明確に特定されており、証拠が揃っている
- 公共性の高い犯罪(例えば通り魔、盗撮、性犯罪、児童への危害など)
- 繰り返し行われており、悪質性・継続性がある
- 他の被害者も複数存在している
これらの要素を満たしていれば、警察も「見過ごせない事件」として捜査に着手しやすくなります。
また、法律上は、警察は市民の被害申告を正当な理由なく拒否することはできません。
実務上、被害届の受理義務は明文化されていないものの、警察法や警察官職務執行法の趣旨に照らして、明らかな被害があるのに受付を拒否することは違法・不当とされうるとする判例や弁護士の見解もあります。
このため、被害届の受付を拒否された場合には、
- 「なぜ受理できないのか、書面での理由説明を求めます」
- 「警察署長または監察官室に正式な苦情申立てを行います」
と冷静かつ明確に伝えることで、対応が変わるケースがあります。
 被害者が検察官のつもりで行動する
被害者が検察官のつもりで行動する
【最後に】
警察が被害届を受け取らない、動かない――これはあなた個人の問題ではなく、構造の問題です。
しかし、だからといって泣き寝入りするしかないわけではありません。
- 被害の証拠を緻密に揃える
- 法的な根拠を把握する
- 告訴の準備を含めて専門家と連携する
- 警察内部の監察制度や苦情制度も使う
そういった一つひとつの行動が、あなたの被害を“事件”として扱わせる鍵になります。
 刑事ドラマのようには一切動かない
刑事ドラマのようには一切動かない
掲載情報につきましては当社が独自に調査、検証および収集した情報です。
情報の妥当性や確実性を一切保証するものでなく、情報や内容が訂正や修正、変更されている場合があります。 よって、当社サイトの利用により生じたいかなる損害等についても運営側にて一切の責任を負いません。掲載情報の修正・変更等をご希望の場合はお知らせください。